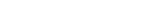――小説を初めて書いたのはいつごろですか? きっかけと内容を合わせてお聞かせください
初めて小説を書いたのは、就職に悩み、この先いかに生きていくべきかと考えていたときでした。おもむろに駅前の本屋へと出向いた私は、『公募ガイド』を購入したのです。
小説を書こうと、このときすでに心に決めていました。
これで大丈夫だと、なにも成していないにも関わらず、どこか誇らしげな気持ちで帰宅したときの夕焼けがとても綺麗だったことを、今でもよく覚えています。
就職に悩んでいたのなら、読まなければならないのは『公募ガイド』ではなく求人誌なのでは? と、思われるかもしれません。まったくもって、そのとおりです。私もそう思います。しかし、私はただ就職先を探していたわけではありません。
これは、なにか適当にバイトでもして、向いていなければ辞めてしまえばいいや、などといった次元の話ではないのです。この先の人生をどう生きていくべきか。自分は果たしてなにをやりたいのか。そういう壮大な宇宙規模の話なのです。
そのように、己の人生に真正面から向き合い、すべてを懸ける覚悟を持って何者かになろうとする人間は、自然と『公募ガイド』を手に取るものなのです。
そんなこんなで小説を書きはじめた私ですが、その内容はといえば、短編小説よりも短い、ショートショートのようなもの――どころか、本当に短いコントのようなものでした。私は、一冊の本になるような長い話がまったく書けなかったのです。
短めのコントのような話で、『神様の神様』みたいなものを書いていました。
ごくふつうの青年が、ある日突然神様の神様になってしまって、そんな主人公のもとに人間からのさまざまな無理難題なお願いを抱えた神様が「自分の力だけでは解決できない。神様助けて!」とやってくる、といったタイトルそのままの話です。
ヒロインというか、主人公の相棒になる女の子がカレーの神様で、とにかくスパイスくさいという設定でした。なぜそんな設定にしたのか覚えていませんが、デビュー作の『ヒキコモリパワード メタルジャック!(メタル)』では、表紙の女の子は出てこないみたいなことをやっているので、おそらくひなた作品のヒロインは、ただカワイイというだけでは務まらないものなのでしょう。

――自身に影響を与えた作品のタイトルと、好きだった点をあわせてお聞かせください
影響といえば、これまで見聞きしたこと、触れ合ってきたものすべてからなのですが、ここでは映画でも漫画でもなくあえて小説だけに限定してみます。
そこで、ぱっと思いついたのが、久美沙織先生、斉藤洋先生、瀧川武司先生の作品でしょうか。この方たちからは、かなり強く影響を受けているような気がします。
気のせいだよ! と、御三方の本と私の本を読みくらべて叫びましょう。
実際、なにか文体が似ているとか、そういう目に見えてわかるといった影響ではないと思います。しかし自分では気づかず、客観的に見てかなり影響を受けているのではとなる可能性もあるので、やはりみなさんは御三方の本と私の本を読みくらべて気のせいだよ! と、改めて叫んでください。
久美沙織先生は、集英社的にはコバルト文庫で活躍された方になるのですが、『ドラゴンクエスト』のノベライズでも有名な方です。
ノベライズとはかくあるべし、といったお手本のような作品になっています。私がノベライズを書くときに意識するのは、当然この久美沙織先生なのです。理想ですね。
斉藤洋先生は、『ルドルフとイッパイアッテナ』シリーズが有名ですね。
作品に対するスタンスとか、あとがきの書き方なんかで影響を受けているかもしれません。『ラッコ11号』のノベライズのあとがきは、まさに斉藤洋先生をイメージして書いたものなのです。
瀧川武司先生といえば富士見ファンタジア文庫の『EME』シリーズですね。現代日本を舞台にした妖怪退治、妖怪保護ものといった内容です。はじめて読んだときは衝撃的でした。それまでの私のライトノベルのイメージは、「ゲームみたいなファンタジーもの」といった感じだったのですが、こんな作品もありなのか! と、目から鱗でした。
文字だけなのに少年漫画。シリアスからコメディーまで自由自在。そんなすごいことを、さらっとやってのけている作品です。
今でも悩んだときや迷ったときに、心の片隅で意識する先生方と作品たちですね。
――プロデビューを志したのはいつ頃からですか? 最初からプロ志向だったのか、何かのきっかけがあったのか教えてください
プロを志したのは、先に述べたように就職や将来のこと、この先どう生きていくのかを意識したときです。趣味で書いていたわけではありません。
最初から、「これでプロになるんだ!」という強い気持ちで書いていました。
私は幼い頃から、この世に生まれてきたからには、なにか自分が生きた証を残したいと常々考えていました。
しかし学生時代の私は、そんな思いとは裏腹に、なにひとつとしてなにかを成し遂げることはできませんでした。
なぜかといえば、私がいつもすべてにおいて受け身だったからです。
小学生になれば、なにかが変わるのではないか。クラスが変われば、なにか劇的なことが起きるのではないか。中学生になれば......高校生になれば......。
ずっとそのくり返しでした。なにかおもしろいことはないものか。余計な面倒を避けるため、言いたいことも言わずに毎日そんなことを考えていました。
しかし、当たり前ですがそんな私になにか劇的でおもしろいことが起きるはずもなく、ただ毎日は過ぎていきます。なにも成せぬまま、ただ時間だけが過ぎていきます。
そしてあるとき、ついに気づいたのです。なにかおもしろいことなんてないのだ、と。待っているだけでは、世界はずっと退屈なままなのだ、と。
では、どうすればいいのか。自分がおもしろくすればいいのです。そのために必要な力はなにか。それは言葉です。世界の退屈も、つらいことも苦しいことも、すべてを喜劇に変えられるのは、言葉によるものしかないと私は考えました。
そして言葉が重なり、連なれば、やがてそれは本となります。本は人類最高の発明です。時間も場所も越えて、誰かの心に届きます。たとえ本そのものが朽ちても、誰かの心の中で、その本に記された言葉は生き続けます。
「見つけた」と思いました。
これこそが、自分が生きた証になるのではないか。
だから私は小説家を目指したのです。
――小説賞に応募する以前、周囲の方に小説を読んでもらうことなどはありましたか? あった場合は他人に読んでもらうことの影響を教えてください
学生時代、本当は帰宅部がよかったのですが、必ずどこかの部活に所属しなければならない決まりがありました。そのときは、いずれプロを目指すことになるとは思ってもみなかったのですが、ラクそうという単純な理由で文芸部に所属していました。
当初は幽霊部員でいいやと思っていたのですが、そして実際幽霊部員も多かったのですが、結果的に私は毎日のように部に顔を出すことになりました。
同じクラスで話の合う友人がいたというのもひとつの理由でしたが、どちらかというと、それは建前に近いものでした。
部には、美人で明るくて誰に対しても気さくな先輩がいました。先輩に会いたくて、私は毎日部室に顔を出していたのです。先輩はプロデビューを目指して小説を書いている人でした。すでに、ある小説賞の最終選考に残っていて担当編集者も付いていました。
顔は良いわ頭は良いわ、それでいて人に嫌われたり妬まれたりもしないほど性格も良いわ、それどころか若くして小説の才能もあるわという、天が二物どころかすべてを与えているといった、思わず「空想上の完璧人間かよ!」と叫びたくなるような人でした。でも、世の中にはそういう人っているものです。
誰も口にしませんでしたし、なにか抜け駆けのようなこともなかったのですが、たぶん部にいた人たちは、みんな先輩のことが好きだったのではないかなと思います。
そんな先輩が、ある日私に言ってくれたのです。
「きみは本当はおもしろいんだから、もっと素直に書いてみればいいのに」と。
恥ずかしい話ですが、そのときの私はいわゆる年相応といいますか、斜に構えてわざと難しい言葉や漢字などを使ってひねくれた話を書いていたのです。
しかし、憧れの先輩がわざわざそう言ってくれたのだからと、私も素直に自分の思ったことを書いてみるようにしたのです。すると、それを読んだ先輩は目に涙を浮かべながらクスクスと笑ってくれたのです。そして、
「ほら、やっぱりこっちのほうがいいよ」
と、喜んでくれたのです。それが嬉しくて、また先輩の笑顔が見たくて、その日から私は、斜に構えるのをやめて素直に自分の思ったことを書けるようになったのですみたいな話は一切ありませんでした。帰宅部でした。先輩なんていません。誰にも見せずに独学でした。そもそも学生時代に小説なんて書いていません。というか、うちの学校には文芸部そのものがありませんでした。
というわけで、初めて人に読んでもらったのは担当編集者さんが最初ですね。
――デビューするまでJUMP j BOOKS以外の新人賞には投稿されていましたか? 投稿されていた場合はその経験から得られたことを教えてください
みんな大好き『公募ガイド』で、新人賞の募集を探して投稿したり、ネットでいろいろな新人賞を探しては、投稿していました。
すべて独学でした。本やらネットやらで小説の書き方を学んで、手探りの状態でずっと書いていました。それまで私は、本一冊分になるほどの長い話は書けませんでしたが、新人賞に投稿するとなると、多くの新人賞の場合やはり一冊分の分量がないと投稿できませんので、なんとか長い話を書けるように研究を重ねました。しかし、苦労して完成させて投稿しても、どれも一次選考すら突破できませんでした。
ネット上などによく、『一次選考は小説の基本的なカタチさえできていれば突破できる』なんて書かれていたりしますが、あれは嘘ですね。いや、やっぱり基本すらできていなかったから落とされたのかもしれません。
そんな状態でしたが、常に心の中では自分はプロになるんだ――いや、むしろもうプロなんだくらいの気概を持って書いていました。
もちろん新人賞を獲ったわけでもないですし、一次選考すら突破できていないのにプロなんだと思うことはつらいことです。実際プロではないのですから。
しかし、大切なことは、今書いているこれが賞を獲って、明日にはもう全国の書店に並ぶかもしれないと明確にイメージすることなのです。そうなると、新人だからとかそんなものは関係ありません。ベテランの作家さんや、超売れっ子の作家さんたちとも同じ土俵で戦わなくてはならないのです。
そういった自覚、イメージを強く思い描きさえすれば、自然と投稿する作品の細部に神が宿るようになるのではないでしょうか。
そして、常に挑戦をしようと意識しながら書いていました。前に投稿したものと似たり寄ったりのものをいつまでも書いていてもしかたがないのです。
つぎはこうしてみよう、ああしてみようと、ひとり試行錯誤しながら、いつもなにか新しいことを取り入れるようにして投稿するようにしていました。
――なぜジャンプ小説新人賞に応募しようと思ったのかを教えてください
まず、積み重ねの大切さという話をさせてください。たとえば、世界一のマラソン選手も、子供の頃からなんの練習もせずにいきなりフルマラソンを完走できていたなんてことは、まずありえません。コツコツと練習を積み重ね、努力をして完走できるようになり、その果てに世界一へと輝いたであろうことは、直接見ていなくともわかります。
職人さんなどもそうです。指先の感覚だけで機械以上の精密さでものづくりをするといった人たちでも、最初からそんなにうまく簡単にできたなんて人はいないはずです。
すべて、長年にわたる努力、コツコツとくり返してきた、たゆまぬ積み重ねがあってのことだと思います。
将来に悩んだ私は、ではこれまでの人生で、自分はいったいなにを積み重ねてきたのだろうかと考えました。
なにもありませんでした。私の目の前に積まれていたのはジャンプだけでした。
雨の日も雪の日も、つらいことがあった日も、修学旅行の日も受験の当日も、私の手にはいつもジャンプがありました。
たとえば、幼い頃からなにか楽器でも習っていれば、長年コツコツと練習を積み重ねてさえいれば、今頃はプロとは言わずとも人に自慢できるくらいに上手くなっていたかもしれないと思いました。
あるいは、子供の頃からずーっと絵を描いていれば、努力を積み重ねてさえいれば、今頃は胸を張って人に見せられるような素敵な絵を描けたかもしれないと思いました。
しかし私にはそんなものはありません。私が積み重ねてきたものは、読み終わったジャンプだけだったのです。「集英社ァ......」と、私は泣きながら買ってきたばかりのジャンプを開きました。DえもんにすがりつくN太のようにです。(編集部注・この流れでよりにもよってなぜ他社の作品で例えてしまったのか......)
その号には、小説賞がリニューアルするという告知が載っていました。
ぱっと開いたページがそれだったのです。運命を感じました。
天啓というやつでしょうか。これまで積み重ねてきたものが、青春のすべてを懸けたものが、私を呼んでくれているように思えたのです。
――応募作はどれぐらいの期間をかけて書かれたのでしょうか? また、応募するとき自信や手ごたえはあったのでしょうか?
正直に申しますと、あまりよく覚えていません。ただ、それほどまでに苦心した、時間がかかったという印象はないので、ふつうのスピード、もしくはそれなりに調子が良ければ、ふつうよりか短い期間で書き上げていたのだろうと思われます。
そもそも、応募作だけでなく小説を書きはじめてからというもの、書いている間の記憶が曖昧なことが多いのです。いつも無我夢中でやっているからでしょうか......。
応募作の自信や手応えですが、コツコツと小説を書いては投稿するという生活を送っていたので、毎回いつも自信たっぷりで応募していました。だいたい、自信がなければ応募などしません。ただ、その自信が根拠のない自信だったというだけです。謎の手応え!
ジャンプ小説新人賞に応募したときも、「前書いたやつよりも上手く書けた」くらいの感覚でした。
絵などではよく言われることですが、小説も基本的には書けば書くほど上手くなるものなので、とにかく前に書いたものより少しでもいいものを書こうとやっていけば、いつかかならず花開くときがくるのではないかなと思います。
私は他の作家さんにくらべてとくに成長が遅いタイプかなと思っていますが、十年くらい書き続けて、やっと昔より少しは上手く書けるようになったかなと感じています。
この感覚だけは、根拠のない自信などではなく、確かなものです。
次回更新は12月11日予定!!
初の編集部訪問はリアルに震えた!?
お楽しみに!!